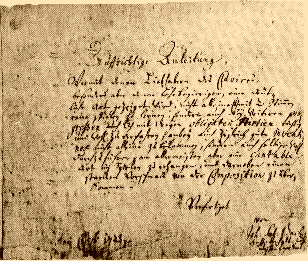インヴェンションとシンフォニア
(BWV 772−801)
《インヴェンションとシンフォニア》 (BWV 772-801)は若い音楽家の育成に主眼を置いて作曲された小品集であるが、芸術的香りを持ち合わせた逸品として弟子の間で定評があった。
前半の2声の15曲を《インヴェンション》、後半の3声の15曲が《シンフォニア》と題されているものの、数の上でも調の配列の面でも明白に対となっており、バッハが1723年に書いた浄書譜一冊に丁寧に収められている。このことから、1つのまとまった作品として意図されたものであることは間違いない。どちらの曲ひとつをとっても、この比較的小さ目の横長の音楽帳を開いた時の2ページに収まる短いものだが、その限られたスペースの中でバッハは対位法技法を紐解くと同時に、様々なスタイルを用い、動機を論理的に発展させることにより、表現の可能性を追究している。
Inventio 1
この曲集は《平均律クラヴィーア曲集》と同様、生前には出版されなかったものの、筆写譜を通じて広く知られるところとなり、1801年に初めて出版が実現した。それ以来、《インヴェンションとシンフォニア》はピアノ教育の一環として広く活用され続けている。しかし、2世紀半以上経過した現在、バッハの意図がどこまで正しく理解され、教育の現場で役立てられているかという点においては、疑問を感じている人も多いのではなかろうか。単なる両手の独立を目的としたテクニカルな教材として用いられる場合などは、特に残念だ。バッハの意図を完全に取り違えているからである。教育者として名声の高かったバッハからの恩恵を受けるには、純粋に音楽を理解しようと努めるにのみならず、バッハの抱いていた価値観を真剣に探らねばならない。それを見出し、理解しえた時、学習者はこの曲集から音楽の普遍的原理を学ぶことができるのであり、同時に感動を覚え、勇気づけられるのである。
目次
表題とその歴史的背景
成立過程と改訂の歴史
曲集の構造
ジャンル、形式とスタイル
弟子に見るバッハの教授法
表題とその歴史的背景
現在ベルリンの国立図書館に保管されているバッハの手による浄書譜は、次のような表題で始まる。
率直な手引き。
クラヴィーアの愛好者、特に学習熱心な者が(1)2つの声部をはっきりと弾けるようにするだけでなく、上達した時には(2)3つのオブリガート声部を正しく、満足のいくように処理することができるように。また、同時に優れたインヴェンション(楽想)を取得するにとどまらず、それをうまく発展させられるように。そしてとりわけ演奏時にあたっては、よく歌う奏法を身につけ、作曲を学ぶための基礎を養うように。
| 1723年 |
アンハルト・ケーテン侯宮廷楽長ヨハン・セバスティアン・バッハが作成す |
|
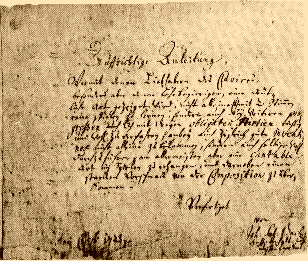
|
バッハはこの表題の中で「インヴェンション」という語を使っているが、言うまでもなく、これは以下に続く15曲の題名にかけている。今日では、音楽で「インヴェンション」と言えばこのバッハの曲集を指すほど有名になってしまったが、この言葉は本来、修辞学の用語であって、ここでのバッハは、作曲にあたってのテーマとなるアイディアをうまくつかむこと、つまり「着想」という意味で用いている。すなわち、この「率直な手引き」は、優れた楽想を見出し、それをいかに発展させ、曲へと実現していくか、という命題に対する答えを見本として提示したものである。それを弟子たちにあてがうにあたって、演奏を志す者には機械的な指の練習からより音楽的飛躍を、また作曲を学ぶ者には、着想のしかたと発展のさせ方のすべの取得を期待しているのだ。
この「インヴェンション」という概念は当時の作曲法の重要な一過程をなすもので、それは当時のドイツで広く学ばれていた古代ローマの政治家・雄弁家・哲学者キケロの修辞法に由来する。『デ・インヴェンツィオーネ』と題した論文の中で、キケロは、演説を書き上げる過程として着想(インヴェンツィオ)、配列(ディスポズィツィオ)、様式(エロクーツィオ)、記憶(メモリア)、演説(プロヌンツィアツィオ)の5つを挙げており、「演説者は、言わんとするところは何なのか、はじめにはっきりさせておくこと。そして発見した事柄を処理し、整理するにあたっては、整然と筋道をたてるだけでなく、鑑識眼をもち、それぞれの論点の重要性を正確に識別せよ。次にそれらを様式で飾るように配列する。そして、それらを記憶に留めるべきである。そして最後に効果的かつ魅力的に述べるのだ。」と、説いている。
修辞学における演説の着想と発表という概念は、そのまま音楽の作曲と演奏に当てはめられた。音楽に対するこのような考え方は17世紀のドイツ音楽理論にすでに現れており、C.ベルンハルトは、「作曲においては、着想(インヴェンツィオ)、推敲(エラボラーツィオ)、演奏(エクセクーツィオ)、以上3つの過程があり、修辞学との密接な関係がある」と述べている。この作曲過程の定義はバッハの世代に至っても議論の対象としてあり続け、J.D.ハイニヒェン、J.マテゾン、J.A.シャイベ等によって熱心に論じられた。その結果、定義が再び細分化され、優れた着想の他に、それに続く配列の概念と様式に沿った発展も大切な過程であると再認識された。この新しい伝統に基づいて「率直な手引き」は、優れた楽想の取得とその上手な展開を実践で説いているという解釈も可能であろう。特に、簡素で快活な楽想が限られた短い空間の中で多彩かつ論理的に展開される様は実に見事で、これこそ音楽における修辞法の模範とも思えてくる。
この表題には「率直な手引き」の使用にあたってのバッハの細かい指示が散りばめられているが、同時にそこから読み取れるバッハの境涯を併せて考察していくと、その指示がより立体的に見えてくる。まず、「率直な」(auffrichtig)という語であるが、この語は「正直な」と「誠実な」という二つの意味を含蓄しており、真剣に学習に励んでいる弟子たちの有益な手引きとなるよう、その目的と願いをストレートに打ち出しているバッハの姿が背後にある。また、この辛辣な表現からは、音楽の力と意義を若い世代に伝授するにあたって、ルター正統派の伝統を踏襲するバッハが示した真摯な態度さえ感じ取ることもできる。このような具体的な説明句は、当時刊行されていた学術書の慣習でもあることから、バッハの責任ある公言と解釈してよいであろう。
次にバッハは2声の演奏技術の習得を説き、それが成就された時に初めて3声の課題へと進むように指示を与えている。この「まず2声を成就する」という学習法は、ルター時代からの伝統で、その当時のトーマス・カントルを努めたG.ラウのポリフォニー音楽集《ヴェスペラルム・プレクム・オフィツィア》(1540年)にもすでに見ることができる。その序文でラウは、「若い学徒が神を賛美し、聖書から真実を学ぶ手助けができること、またそれを通して栄誉ある学問としての音楽を愛し研究されんことを、特に常日ごろから望んでいる」と述べている。ここにバッハの《インヴェンション》の様式、作曲技法、それに教育の目的に通ずる確固とした伝統が確認できることは特筆すべきであろう。
表題を締めくくっている「歌う奏法」というくだりにおいては、後の世代のレガートを基調とした「カンタービレ奏法」と混同されることもあるが、ここでは、18世紀初期の演奏習慣の枠内で解釈しなければならない。ここでは、歌手が言葉の意味を汲んだうえで明瞭に発音しなければならないように、鍵盤楽器奏者は個々の旋律を弾く際に明確なアーティキュレーションを施さねばならない、と解釈すべきであろう。それは、対位法音楽の神髄でもある「各声部の独立が調和をもたらす」という理念であり、作曲の基本となる概念の一つでもある。
《インヴェンション》の表題には以上のような理路整然とした歴史的背景があり、バッハが生きた「時」とバッハ自身の反応を今日の私たちに語りかけてくれる。
成立過程と改訂の歴史
この曲集の成立を論じる時に切り離せないのが、その前身となった《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集》である。表表紙の裏に記された「1720年1月22日」は、父子間のクラヴィーアのレッスンが正式に始まった日を指すのであろう。長男がちょうど9歳と2ヶ月の時であった。
ここにみる父の指導は感心するほどに思慮深く体系づけられている。まずバッハは、フリーデマンに楽譜を読むに当たっての基本を教え、多種の装飾記号のリアライズ法、指使いの練習へと続いていく。そのアプリカーツィオがこの小曲集の第1曲目で、はじめにバッハは、J.N.J(In
Nomine Jesu=イエスの御名にて)と記した。長男の教育に情熱を惜しみなく注いだ父の姿が目に浮かぶようだ。この音楽帳には、演奏技術や様々な形式とスタイルの体得を目的とした小品群62曲が収められているが、この前半には、指の練習を主眼とした曲が多く、簡素なコラールプレリュードや舞曲に続いて、《平均律クラヴィーア曲集》の前身となった11のプレリュードの初期稿も収められている。
15曲の《インヴェンション》の初期稿(ここではプレアンブルムと題されている)は、この音楽帳のほぼ中間である第32番目から始まっている。G.P.テレマンの組曲とG.H.シュテルツェルのパルティータがこれに続き、最後に15の《シンフォニア》の初期稿(ここではファンタジアと題されている)が来るように配置されている。現在アメリカのイェール大学の図書館に保管されているこの貴重な音楽帳は、既に製本が崩れてしまっており、楽譜2枚分が残念ながら喪失してしまっていた。ここには14番目のファンタジアの後半と15曲目が記載されていたはずである。
こうして全体をみてみると、この音楽帳は、長男の演奏技術が徐々に上達していく様子が反映していることに気づかれよう。この後半にあてがわれた《インヴェンションとシンフォニア》の初期稿においては、すでに基本的な演奏技術に関した問題を克服済みのフリーデマンに対して、本格的な対位法を教えてみようと思ったのかもしれない。また、当時すでに草稿が進んでいた《平均律クラヴィーア曲集》からヒントを得て、より体系的な教材を書こうと思い立ったのかもしれない。実際、これに先行する第31番目の曲がこの音楽帳に含まれる唯一のフーガ(BWV
953)であるが、単なる偶然とは思えない。このバッハの筆跡はかなり後のもので、後に空白のページに書き込まれたと考えられているが、曲集が対位法の使用の有無という点でシンメトリー構造になっているところがいかにもバッハらしい。
このシンメトリーを更に追求していくと、15のプレアンブルムの構造にもそれが存在することがわかる。一番外側の第1番と15番が2拍子系で、その内側の第2番と14番が3拍子系という具合に、中心部の2拍子系の5曲(第6から10番)まで、2拍子系と3拍子系が交互に層をなしているのだ。3声のファンタジアには、このような規則性は見当たらない。
また15のプレアンブルムの構造には、明確に体系化された作曲様式が具体化されており、3曲づつの小さなグループを形成しているのも見逃せない特徴だ。まず、はじめの3曲(C,
d, e)では、テーマが音階を基調としたもの、次の3曲(F, G, a)ではテーマに主和音が分散化されており、さらに続く3曲(h,
B, A)では、息の長いテーマと対主題がみられる。これらの特徴は、学習課程の進め方というよりは、作曲時の勝手が反映していると見るのが妥当であると思われる。
この音楽帳をより細かく見ていくと、楽譜作成時のより詳しい状況が手に取るように窺える。フリーデマンが写譜した数曲を除けば、全てバッハの自筆譜であるのがわかる一方、浄書譜は数えるほどしかなく、殆どが作曲上の改訂を多く含む草稿譜であることが明るみになる。推敲の後もあちこちに見られ、数々の改訂箇所にバッハの作曲の軌跡を垣間見ることができる。特に、ハ短調とト短調のプレアンブルムでテーマの形自体が後で変えられているところなどは、バッハの作曲の進め方を考察する上でも大変貴重な資料である。
これらが作曲初期にみられる改訂であることは、その前後関係から原因を探ってみれば明らかになるが、バッハは《インヴェンション》の浄書譜を書いている段階でも同様に改訂の手を加えている。
例えば、インヴェンション第7番(e)と13番(a)は、初期稿ではどちらも21小節であり、共に3つの均等な長さをもつフレーズにより構成されていたのだが、最終稿では、共に第3フレーズがいじられ、それぞれ23と25小節と長くなっている。他の楽章でも、細かい箇所に手が加えられており、単なる写譜の作成とはかなり趣が違っていた。
バッハがかなり後になって加えた改訂に冒頭のハ長調のインヴェンションがある。この主題は16分音符を基調としているが、その2拍目にあたる3度の下行跳躍にバッハは経過音を挿入し、3連符の動機を新しく据えた。この改訂により、曲の性格がより流麗になったが、その直接のきっかけが何であったのか、意見の分かれるところである。バッハは、弟子とのレッスンの間に、このように動機に変化をもたせることが可能であることを例として示したものなのか、それとも純粋に曲の内包する性格をより明確化したものなのか。答えは出ていない。
曲集の構造
二つの小曲集《インヴェンション》と《シンフォニア》は、共に15曲から構成されているのはすでに述べた通りであるが、その構成内容とバッハの意図するところも探ってみる価値があろう。
まず、どちらもハ長調で始まり、それぞれの調の主音が半音階を上行するかたちでアレンジされており、同じ調の重複が意識的に避けられているところに注目されたい。同じ主音上に長調と短調が両方存在する場合には、《平均律クラヴィーア曲集》の場合と同様に、長調が先に来るように配置されている。このように、《インヴェンション》と《シンフォニア》は同時期に書かれた《平均律》とよく似た構造を呈している。似ていない所はといえば、24全ての調を網羅せず、「15の調」のみを採用していること、それからプレリュードとフーガに見られる「対の概念」がここでは別の次元に据えられていることであろう。
とりわけ重要なのは、バッハはどういう考えをもって「15の調」を選択したのかということである。これは、フリーデマンの音楽帳に含まれる初期の稿に戻って考察を進める必要がある。
この曲集はすでに見てきたように、バッハが長男の音楽教育をある程度推進してきた段階で、より高度で体系的な曲集を念頭に置つつ構築していった結果の賜物である。その体系化という目標に《平均律》で可能性を探究した「調」がここに対象として含まれることになったと見てよいであろう。実際、この15の調は、マテゾンが著書「新設のオーケストラ」(1713年)で解説した16の調のはじめの15であることもその大きな根拠である。つまり、当時非常に稀にしか用いられなかった調にあたっては、バッハはここで割愛したのである。
バッハは、まずハ長調の音階上の三和音を主和音とする調を上行形に並べた(C,
d, e, F, G, a, h)。残りの8つの調は、音階を下行する形に並べられた(B, A,
g, f, E, Es, D, c)が、特定の音階上に沿っているわけではなく、残り物を適当に割り振ったものである。しかし、この調構造は、シンメトリックな構造を呈していることから、意識的に体系化されたものであるに違い無さそうだ。その一方、最初の6曲では調記号中の嬰変記号が1つ以下、第7から8曲では2つ、第9曲で3つ、さらには第11から12曲では4つという具合に、比較的易しい調から順番に学べるように構築されている。共に15曲の《プレアンブルム》と《ファンタジア》が同じ構造を取っていることから、バッハはこの体系を写譜段階以前に決定したと考えてよいであろう。つまり、バッハは一つのまとまった15曲を二つの小グループに分けるにあたって、構造美と教育上のメリットを同時に考慮したのである。これと似た体系はまた、同じ音楽帳に記載された《平均律》の前身である11のプレリュード(C,
c, d, D, e, E, FとCis, cis, es, fにグループ化できる)にも反映していることから、バッハの仕事に首尾一貫性がみられる。
この調体系は《インヴェンション》の1723年の浄書譜では一新され(C, c,
D, d, Es, E, e, F, f, G, g, A, a, B, h)、2つのグループへの分割は姿を消した。この新しい体系は、1722年に新しく確立された《平均律》の調の配列をモデルとしているのであるが、そこでは、ハ長調を出発点として、15の調をアレンジし直す際に、長調と短調の順を守りながら半音階に現われる調をあてがった。最後の第15番は《平均律》でも最後の調であるロ短調である。ここからも、同時期に成立した二つの教育用作品が、それぞれ共に大規模な構造の改変を双方の影響のもとに行われたという事実が確認できる。そこには、長男の教育のために生まれた作品も、多くの弟子の育成にも用いられるにあたってのバッハの意識の変化が背景にあるとみてよいであろう。すべての「クラヴィーアの愛好者、特に学習熱心な者」の使用を念頭に置いた普遍的な教本へと衣更えをしたのである。選曲は生徒の技術的レヴェルによるところが大きかっただろうし、もはや意識的に調の難易度を曲集の表面に出す必要も無くなったのである。これとは逆に、曲を体系的に並べ替えることにより、曲が見つけ易くなったという利点も見逃せないポイントだ。
成立過程を共にするこれらの教育的作品には、その元になる神学的概念に繋がりがあってもおかしくない。かなり大胆な仮説ではあるが、それは曲集に組み込まれた数象徴に潜んでいると考えている。まず、《平均律》の24という数字であるが、ここではヨハネの黙示録に出てくる御座の回りにある24の座と長老たちを示すと解釈されうる。それに対し、《インヴェンションとシンフォニア》の曲数の示す30は、イエスが福音を広めるために出家するまで人間として基礎を学んだ30年を示していると解釈すると筋が通る。つまり、バッハは、神学的意義を内包する2つの聖数を通して、教育の過程を一人前の音楽家になるための基礎作りをすることと、一応の基本的な教育を終了した者が学習に喜びを見出し神の栄光のために更なる研鑚を積むための修行することとに分け、それを曲数で象徴的に表したと見ることができる。バッハは研鑚の意義と神の賛美をここに体現化したのである。
ジャンル、形式とスタイル
この「インヴェンション」という音楽のジャンルは、バッハによって定着することになったのは事実だとしても、バッハによって新しく開拓されたという訳ではない。すでに見てきた《インヴェンション》の初期稿では、バッハは題名を「プレアンブルム」としていたこと、つまり、作曲当時に意図したものではないことが明らかなため、後からの思いつきであることは紛れもない事実である。そのプレアンブルムでさえ、F.フリンデルの研究によれば、エマーヌエル・バッハが回想で語った通り、バッハはその作曲にあたって同時代の優れた作曲家、J.パッヘルベル、A.ヴィヴァルディ、それにJ.C.F.フィッシャー等の作品をモデルにしたとしている。
表題の歴史的背景ですでに見てきた様々な事柄からは、強い必然性が感じられるのだが、なぜここで「インヴェンション」と改名することにしたのか、そのバッハの真意も正確には分かってはいない。これは、3声の方の《シンフォニア》が初期稿で「ファンタジア」と題されていた関係と合い重なる訳で、その理由をもう少し掘り下げて考察してみたい。
まず一番有力な候補としては、F.A.ボンポルティのヴァイオリンと通奏低音のための《インヴェンツィオーニ》(1712年)が挙げられよう。この作品はAnon.5として知られているバッハの弟子の筆写譜の存在により、バッハが《インヴェンション》の自筆浄書譜を完成させたのと同じ1723年に使用していたことがわかっている。さらには、この筆写譜にバッハが数字を記入したことも突き止められているのだ。
《インヴェンションとシンフォニア》の最終稿である自筆譜の表題をみても、それぞれの題名には言及しておらず、わずかに《インヴェンション》という言葉を「着想とその発展」というくだりでわずかに触れているに過ぎない。《インヴェンション》はプレリュードでも2声のフゲッタでもないし、かといって《クラヴィーア練習曲集 第3部》に収められている《4つのデュエット》とも違うジャンルの作品という意味もあったのかもしれない。この尺度でみていくと、バッハはこの曲集を一種独特のものとして捕らえていたようである。何よりもまず、曲集の性格を決定付けているのは、主題の簡潔さと快活さであろう。そして、それらのアイディアを実現化する対位法の技法が、その多くが5度ではなくオクターブで模倣されているということも、主題が提示され展開されていく過程に透明性を与えてくれる直接の要因となっているし、結果的には和声構造が安定するため、転調も論理的に生きてくるようになっている。
これに対して、3声の《シンフォニア》の方は、単に1声増やしたというのではなく、様々な面で曲がジャンルとして明確に別のクラスに属することに由来するものと考える。形式面から考察すると、5度の模倣が頻繁に見られ、くっきりとした経過句を持ち、ソナタ形式を彷彿させるという点で、バッハのフーガに親近性がみられる一方、その多くが比較的自由なバス声部を擁し、その上に対位法的に処理された2つの旋律が展開しているという点から、トリオソナタにも強い類似性がみられる。これは単に曲の長さが長くなっているという点にとどまらず、より息の長い主題が多くなっているという点からも同じ事が言える。ここでは、バス声部が曲の冒頭部で必ず上声部の伴奏として同時に奏されるという点では、他の対位法書法をとったトリオソナタとは異なっている。つまり、《シンフォニア》とはソナタでもフーガでもないジャンルに属するのである。このポリフォニーとホモフォニーの融合は明確な方向性と論理性を曲に与え、古典派のソナタ形式の持つ説得力をすでにここで呈示している。ベートーヴェンのソナタ形式は、この《シンフォニア》をモデルとしたというE.ラッツの主張も、ここにある。
基本的な構造原理を見ても、《インヴェンションとシンフォニア》はバッハの他の大規模な作品とあまり変わらず、単に曲のスケールが小さくなっているに過ぎない。つまり、ここでの1フレーズが他のジャンルの曲では1つのセクションにあてはまる。次のフレーズは展開部にあたり、続くフレーズは曲を締めくくる、というように、縮小された3部形式を構成しているのが常である。もちろん、このパターンに沿わないものもある。例えば、第2番(c)はかなり厳格なカノンであるし、第9番(f)は二部形式である。
対位法技法を取ってみても、かなりの幅が存在する。《インヴェンション》では、厳格なカノン(c,
F)、フーガ様式(G, h)ソナタ形式を彷彿させる二部形式(E)、二重対位法(Es,
E, f, A)、冒頭動機の展開(転回、反復、声部交換など:C, D, d, e, g, a,
B)が主なアイディアとして用いられている。しかし、全体的にみて、対位法技法を厳格に追究しているという訳ではなく、動機に忠実に、そして論理的にかつのびのびと発展させることが優先させられている。これに対して、《シンフォニア》の方は、フーガ様式を踏襲するものが大部分を占めている。数少ない例外の中には、第5番(Es)や11番(g)のように、厳格な模倣を取らないものも混じっているが、特に、第5番はバス上のデュエットという形をとっており、その多種多様の装飾が表情豊かな楽想を見事に醸し出している点で異色である。また、きらびやかな第15番(h)は、その殆どが2声で書かれており、流れるような32分音符と手の交差といった高度な演奏技巧を要求しいる所がとても印象的である。
《シンフォニア》中、対位法的に最も劇的で厳正なのは、第9番(f)であろう。その主題は、修辞的な休止符で特徴づけられたB-A-C-H動機(ここでは移調された形As-G-B-A)から成り、その他に半音階下行を含む2つの性格の異なる対主題を擁している。この3つの声部が衝突し、作り出す不協音には独特の深い悲しみを感じさせる。この強烈なアフェクトと緻密で複雑な曲の構造は、様々な思弁的な議論も呼んできた。その中でもU.ズィーゲレとE.シェイフの数象徴と神学的意義を探求した曲の構造の分析はとても興味深い。
弟子に見るバッハの教授法
バッハが長男を指導していった過程はすでに考察してきた通りであるが、バッハが教えた弟子が残したエピソードからも同様のことが窺える。
バッハの弟子中でも最も優秀で理論家として大成したのはキルンベルガーであるが、その彼によれば、「バッハは最も簡単なものから最も複雑なものまで徐々に一歩づつ進み、それが結果的にフーガへと到達する段階であってさえも、1段階上がっていくだけの難しさしか感じさせない。」とバッハの教授法を絶賛している。
バッハの息子、フリーデマンとエマーヌエルから直接情報を得たフォルケルによれば、初歩段階にある弟子に対してバッハは、彼独自の打鍵法を教えることに集中したとのことである。そのために、まず10本の全ての指がはっきりときれいなタッチを習得するまで、特定の演奏技術を習得するための練習句を課題として宛がい、数ヶ月間続けさせた。しかし、それに飽きてきた弟子に対しては、バッハは、いくつかの練習を組み合わせて曲を作ってやったりした。《6つのプレリュード》(BWV
933-938)や《インヴェンション》がこれにあたるらしい。
また、バッハの弟子、H.N.ゲルバーによれば、バッハは《インヴェンション》を彼にまず与え、組曲、《平均律》へと続いたようだ。それは、すでに彼が当時大学生であり、演奏技術の基礎ができていたためであろう。このゲルバーがバッハのもとで学んでいた1725年に作成した《インヴェンション》の楽譜は、現在オランダのハーグ市博物館に保管されている。ここには、バッハに由来すると思われる装飾音もいくつか見られるが、その中でもシンフォニア第5番に加筆された装飾音にはバッハの筆跡と思われるものも含まれている。当然のことながら、これらの装飾はバッハがレッスン中に模範演奏をした際に即興で入れていったものである可能性が非常に高い。
多数の弟子の教育に携わってきたバッハの一番の魅力は、彼の用いた教材の素晴らしさや名声を博した演奏能力ではなく、彼の弟子に対する真摯な態度と思いやりのある優しい人柄であった。
「わたしは一所懸命に励んだのだ。一所懸命に励むものは誰でも、このぐらいにはなれるのだ。」
という格言をバッハが残したそうだが、これは、なかなか上達できないで苦しんでいるいる弟子を激励するために言った言葉であろう。また、病気で苦しみつつレッスンに出てくるキルンベルガーを見かね、バッハが代わりに出かけていったことがあったそうだ。溢れる感謝の気持ちをいかに表わそうかと心底悩んでいるキルンベルガーにバッハはこう言ったそうである。
「キルンベルガーよ、感謝などしないでくれ。わたしは、音の芸術を君がその心から学ぼうとしてくれるだけで嬉しいんだよ。わたしが知ることになっただけのものを、君が君自身で学んでいるということだけじゃないか。わたしへの感謝の気持ちなどはいらないんだよ。今度は陳腐なものに物足りなくなった他の優秀な学生のために君が少しでも役に立ってくれることを約束してくれればそれでいいんだ。」と。
(c) Yo Tomita
1999
|
このエッセイは、キングレコードよりリリースされた鈴木雅明氏のCD(KKCC−2290)の楽曲解説として書いたものです。
|